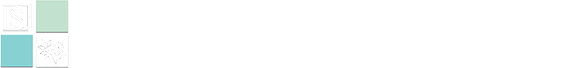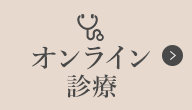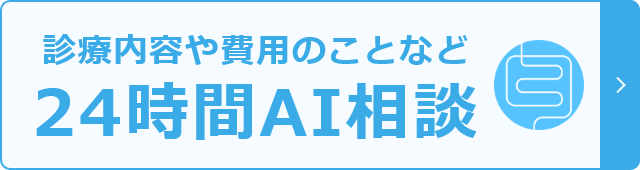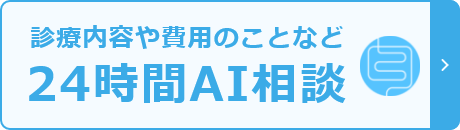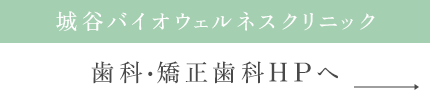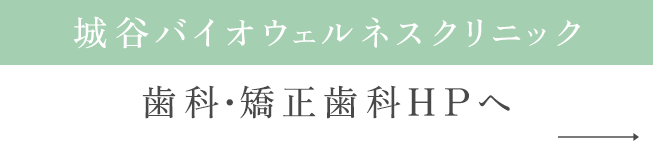当院はホリスティック(包括的な)医療をご提供するクリニックです
 当院がご提供するホリスティック医療は、症状の一部分だけを見るのではなく、「身体・心・環境・微生物」のつながりに着目し、全体のバランスを整えることを目指しています。
当院がご提供するホリスティック医療は、症状の一部分だけを見るのではなく、「身体・心・環境・微生物」のつながりに着目し、全体のバランスを整えることを目指しています。
医科と歯科が連携し、口腔から腸までの消化管全体を包括的に診るとともに、腸内フローラ移植(FMT)や分子栄養療法、マイクロバイオーム解析(細菌の遺伝子検査)などを活用します。微生物との共生を軸とした「微生物循環学™」の考えのもと、自然治癒力を高める医療を実践しています。
さらに、患者様お一人おひとりのライフスタイルや体質に合わせた個別ケアを行い、「なぜ不調が起きたのか」という根本原因に向き合います。農・食・歯・医をつなぐ「Agri-Dent-Medicine™」の理念も取り入れ、心と体の調和を取り戻す医療を目指しています。
内科
当院の内科の特徴
 内科では、生活習慣病、更年期障害、その他頭痛・めまい・ふらつきなどの症状に幅広く対応します。「なんとなく調子が悪い」という時にも、お気軽にご相談いただければと思います。
内科では、生活習慣病、更年期障害、その他頭痛・めまい・ふらつきなどの症状に幅広く対応します。「なんとなく調子が悪い」という時にも、お気軽にご相談いただければと思います。
また当院では、必要・ご希望に応じて、消化器内科・心療内科・歯科とも連携し、総合的な治療・予防を行うことができます。
こんな症状は内科までご相談ください
- 頭痛
- 胸痛
- 動悸、息切れ
- 下痢、便秘
- めまい、ふらつき
- じんましんなどの皮膚症状
- ほてり、不眠、むくみ、イライラ など
内科で対応する病気
- 気管支喘息
- 咳喘息
- 気管支炎、肺炎
- アレルギー性鼻炎、花粉症
- 胃腸炎
- 糖尿病
- 高血圧症
- 脂質異常症
- 高尿酸血症、痛風
- メタボリックシンドローム
- 更年期障害
- 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)
- 甲状腺機能低下症(橋本病)
- 帯状疱疹
- 膀胱炎
- 腎臓病
- 不眠症
- がん など
がん内科外来(担当:奥野)
 当院のがん内科では、放射線治療を専門とし35年以上のキャリアを持つ医師が診療を担当しています。これまでに脳神経・頭頸部・呼吸器・消化器・婦人科・腎泌尿器・前立腺・骨や軟部組織・皮膚など、全身にわたる幅広い腫瘍の治療に携わってきました。その豊富な臨床経験を活かし、がんの治療に加えて、緩和ケアや心のサポートにも力を注いでいます。
当院のがん内科では、放射線治療を専門とし35年以上のキャリアを持つ医師が診療を担当しています。これまでに脳神経・頭頸部・呼吸器・消化器・婦人科・腎泌尿器・前立腺・骨や軟部組織・皮膚など、全身にわたる幅広い腫瘍の治療に携わってきました。その豊富な臨床経験を活かし、がんの治療に加えて、緩和ケアや心のサポートにも力を注いでいます。
がん治療には「手術・薬物療法・放射線療法」の三大治療法がありますが、当院ではそれにとどまらず、患者様の価値観や生活に合わせた統合的なアプローチもご提案可能です。
例えば上記のような選択肢を組み合わせ、身体と心の両面から最適な療養法をともに考えていきます。
私たちが大切にしているのは、医師の知見を一方的に押し付けるのではなく、患者様と寄り添いながら、その方に合った治療や養生を見つけていくことです。
特別外来について
副腎疲労外来
副腎は、腎臓の上にある小さな臓器です。二層に分かれており、内側を副腎髄質と呼びます。副腎髄質では、危険な状況を回避するためのアドレナリン、ノルアドレナリンが分泌され、脳の働き・身体の動きを速める役割があります。外側は副腎皮質で、こちらはコルチゾール、DHEA、アルドステロンを分泌しています。慢性的または強いストレスがかかるとこれらのホルモンの分泌が低下しますが、特にコルチゾールの分泌が低下してストレスに対処できなくなった状態が、「副腎疲労」です。
ストレス以外にも、アジソン病という珍しい病気を原因としてコルチゾールの分泌が低下し、副腎疲労を起こすことがあります。
ストレス過多の現代において、アメリカでは約15%が、日本ではそれ以上の人が、副腎疲労の状態にあると推定されています。
※「副腎疲労」は一般病名としては認められておらず、分子栄養学における概念で東洋医学の「未病」や「潜病」に近い概念です。
※ 副腎疲労に関する検査、治療は全て自費診療となります。
内科で対応する検査
- 血液検査
- 超音波検査
- 動脈硬化検査
- 尿検査
- 便検査(便潜血、便培養)
- 簡易型ポリグラフ
自費診療
- 糖化(AGEs)検査
- 自律神経検査
- 体組成計検査(InBody)
- 腸内フローラ検査
- 尿中有機酸検査(OAT)
- SIBO呼気検査
- GI-MAP(精密便検査)
- 唾液検査
- 口腔内細菌顕微鏡検査
- 毛髪ミネラル・重金属検査
- オリゴスキャン(ミネラル重金属検査)
- 睡眠検査
消化器内科
当院の消化器内科の特徴
 当院の消化器内科は、単に胃腸の不調を診るだけでなく、「腸内環境の最適化」を通じて全身の健康を整えることを目的とした統合的な診療を行います。特に、腸内フローラ移植(FMT)やSIBO(小腸内細菌異常増殖)、過敏性腸症候群(IBS)、機能性ディスペプシア(FD)など、慢性的な胃腸の不調に対して専門的なアプローチを実施します。分子栄養学や心身医学、微生物学と組み合わせ、原因に根ざしたケアを重視しています。また、口腔との連携も重視し、「口から肛門まで」一貫して消化管全体を診るスタイルが特徴です。自然治癒力を引き出す腸の医療を提供します。
当院の消化器内科は、単に胃腸の不調を診るだけでなく、「腸内環境の最適化」を通じて全身の健康を整えることを目的とした統合的な診療を行います。特に、腸内フローラ移植(FMT)やSIBO(小腸内細菌異常増殖)、過敏性腸症候群(IBS)、機能性ディスペプシア(FD)など、慢性的な胃腸の不調に対して専門的なアプローチを実施します。分子栄養学や心身医学、微生物学と組み合わせ、原因に根ざしたケアを重視しています。また、口腔との連携も重視し、「口から肛門まで」一貫して消化管全体を診るスタイルが特徴です。自然治癒力を引き出す腸の医療を提供します。
消化器病専門医でありながら、自ら潰瘍性大腸炎発症によって大腸全摘術を経験した腸の専門医
消化器病専門医、消化器内視鏡専門医、内科認定医である院長城谷昌彦は、自身の経験から西洋医学はもとより、東洋医学、自然療法の見地からも腸内環境を健全に保つことの大切さを改めて痛感し、さらに分子栄養学、心理学、精神腫瘍学、運動生理学などを学び、栄養療法などホリスティック(全人的)なアプローチで腸内環境改善を柱とした根本治療を目指しています。
こんな症状は消化器内科までご相談ください
- 胸やけ、胃もたれ
- 吐き気、嘔吐
- 胃痛
- 食欲不振、体重減少
- 便秘、下痢、血便
- 腹部膨満感(お腹の張り)
- 口臭やガス漏れ、匂いが気になる
- なんとなくお腹の調子が悪い
- 消化器症状があるけれど、体質だと思って諦めている
消化器内科で対応する病気
過敏性腸症候群(IBS)
便秘、下痢、腹痛・腹部不快感などの症状が見られ、どの症状が強く出るかは症例によって異なります。内視鏡検査や血液検査を行っても明らかな炎症が見られないため、長くストレスが原因と考えられていました。
しかし近年の研究で、腸内細菌のバランスの乱れを伴うケースが多いことが分かっており、これが過敏性腸症候群の発症に少なからず影響しているものと思われます。過敏性腸症候群の方の腸内では、Lactobacillus、Villonellaという菌が多く見られます。さらに過敏性腸症候群では消化管蠕動運動の問題に伴う腹部の不快感や内蔵知覚過敏があり、脳がストレスを感じるとこれらの症状が悪化することが多く病態を複雑にしています。
便秘症
本来出すべき量の便が出ない、快適に出ず腹痛・排便困難を伴う、残便感があるといった状態を「便秘症」と言います。よく知られている原因としては、食物繊維の不足、運動不足などがありますが、それ以外にも大腸がんやクローン病などの病気が原因となるケースがあります。また、腸内フローラの乱れによって引き起こされる便秘も少なくありません。
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)
潰瘍性大腸炎は、下痢、下血、腹痛を伴う大腸の炎症性疾患です。比較的若い方に発症し、ひどい腹痛・下痢によって日常生活に支障が出ているケースも少なくありません。自己免疫疾患の一つと考えられていますが、腸内細菌のバランスの乱れ(dysbiosis)も原因の1つになると考えられています。厚生労働省より難病の指定を受けていますが、適切な治療を行うことで、健康な人と変わらない生活を送ることが可能です。
クローン病は、小腸・大腸を中心に慢性的な炎症が見られる病気です。潰瘍性大腸炎と同じく、自己免疫疾患と考えられており難病の指定を受けています。主な症状として、下痢、下血、腹痛が挙げられます。潰瘍性大腸炎と違うのは、口から肛門まで、すべての消化器疾患で炎症が起こり得るという点です。
専門外来について
小腸内細菌異常増殖症(SIBO)外来
本来、小腸は大腸と比べて細菌の数が少ないのですが、小腸内細菌異常増殖症ではその小腸の細菌が増殖し、ガスを発生させ、主に食後にさまざまな不快な症状を引き起こすことがあります。
小腸内細菌異常増殖症は、比較的新しい概念で、診断に至らないケースが少なくありません。海外の調査によると、過敏性腸症候群と診断された方のうち、約6~8割が小腸内細菌異常増殖症を合併していたことが分かっています。当院は、小腸内細菌異常増殖症の診断のためのSIBO呼気検査を導入しています。
※「小腸内細菌異常増殖症(SIBO)」はまだ一般病名としては認められていません。
※ SIBOに関連する検査、治療は全て自費診療となります。
消化器内科で対応する検査
- 尿検査
- 血液検査
- 超音波検査(腹部・頸部)
- 尿素呼気検査(ピロリ菌検査)
- 便検査(便潜血、便培養)
※内視鏡検査が必要な場合は連携病院をご紹介いたします。
自費診療
- 腸内フローラ検査
- 尿中有機酸検査(OAT)
- SIBO呼気検査
- GI-MAP(精密便検査)
- 遅延型フードアレルギー検査
- 腸管バリア検査
- 唾液検査
- 口腔内細菌顕微鏡検査
- 口臭測定検査
心療内科
 当院の心療内科は、ストレスや自律神経の乱れ、不安・不眠・慢性疲労など、身体と心の不調が重なった状態に対し、根本原因からの改善を目指す統合的アプローチを行います。薬に頼るだけでなく、腸内環境・栄養状態・ホルモンバランス・生活習慣など、多角的な視点から心と体を整えます。特に「腸と脳のつながり(腸脳相関)」を重視し、腸内フローラ移植(FMT)や分子栄養学、微生物学を取り入れた診療を行います。不調の奥にある声に耳を傾けながら、健やかな日常へ導いていきます。
当院の心療内科は、ストレスや自律神経の乱れ、不安・不眠・慢性疲労など、身体と心の不調が重なった状態に対し、根本原因からの改善を目指す統合的アプローチを行います。薬に頼るだけでなく、腸内環境・栄養状態・ホルモンバランス・生活習慣など、多角的な視点から心と体を整えます。特に「腸と脳のつながり(腸脳相関)」を重視し、腸内フローラ移植(FMT)や分子栄養学、微生物学を取り入れた診療を行います。不調の奥にある声に耳を傾けながら、健やかな日常へ導いていきます。
こんな症状は心療内科まで
ご相談ください
- 気分の落ち込み
- 意欲の低下
- 不安感
- イライラしやすい
- 集中力の低下
- 落ち着きがない
- 眠れない
心療内科で対応する病気
心身症
心身症とは、身体疾患のうち、発症や悪化に心理社会的ストレスが影響して機能的な障害が生じた疾患群を指します。仕事や対人関係における心理社会的ストレスに無頓着である場合、無自覚な場合に発症・悪化するケースが目立ちます。
心療内科では、身体の症状とストレスのあいだの心身相関を理解することに重きを置き、診療します。
なお、上記の疾患群の具体例としては、過敏性腸症候群や機能性ディスペプシア、本態性高血圧、緊張型頭痛・片頭痛、疼痛性障害、アトピー性皮膚炎などが挙げられます。
パニック障害
パニック障害とは、動悸・胸痛・呼吸困難・めまいなどの身体の症状と、このまま死んでしまう・狂ってしまうという強い恐怖心が突然現れ、またその発作が繰り返される疾患です。発作が再び起こることへの不安から、発作が起きた場所・場面を避けるようになり、日常生活に支障が出ます。
治療では、抗うつ薬などを用いた薬物療法、認知行動療法が有効になります。
抑うつ状態
誰もが経験する、悲しいこと・辛いことを受けて気分が落ち込んだ状態を「抑うつ気分」、その状態が続いた場合を「抑うつ状態(うつ状態)」と言います。さらに、そのことで日常生活に支障が出ている・苦痛が強い場合に、「うつ病」と診断されます。
抑うつ状態は、必ずしもうつ病によって引き起こされるとは限りません。双極性障害や統合失調症、適応障害、パーソナリティ障害、認知症などが原因になることもあります。
不眠症
睡眠障害のうち、もっともよく見られるのが不眠症です。安眠できない・快眠できない状態が続いている状態を指し、何時間眠れているかは関係ありません。つまり8時間睡眠をしている人でも、安眠・快眠ができていない状態が続いているのであれば、不眠症と診断されます。
不眠症は、うつ病などの精神疾患の症状として現れることのほか、睡眠時無呼吸症候群(SAS)のように気道の閉塞が睡眠の質を低下させていることもあり、診療ではその原因についても正しく見極めていくことが大切になります。お仕事、勉強を含めた日常生活に少しでも支障が出ていると感じる場合は、お気軽にご相談ください。
自律神経失調症
自律神経失調症とは、食事の変化、睡眠の不足、ホルモンバランスの変化、ストレスなどを原因・きっかけとして自律神経のバランスが乱れ、心身に症状が現れた状態です。倦怠感・疲労感、動悸、頭痛、ほてり、しびれ、のどの違和感、多汗、頻尿、下痢・便秘、イライラ、不安など、さまざまな症状が見られます。日常生活に支障をきたし、悪化して外出が困難になるというケースも見られます。症状が気になった時には、お早目にご相談ください。
専門外来について
発達支援外来

当院の発達支援外来では、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠陥多動障害(ADHD)、学習障害(LD)などの発達特性を持つお子さまとそのご家族に寄り添い、心と体の両面からサポートする統合的な診療を行っています。特に「腸と脳のつながり(腸脳相関)」に注目し、腸内フローラの改善や分子栄養療法を通じて、情緒の安定や集中力の向上をめざします。さらに、噛む・飲み込む・呼吸するなどの口腔機能にも着目し、歯科や口育士との連携による全身的な支援を行っています。一人ひとりの特性や生活環境に合わせた丁寧なサポートで、子どもたちの「育ち」にそっと寄り添います。