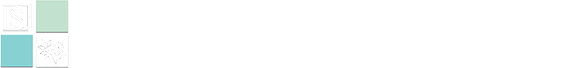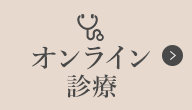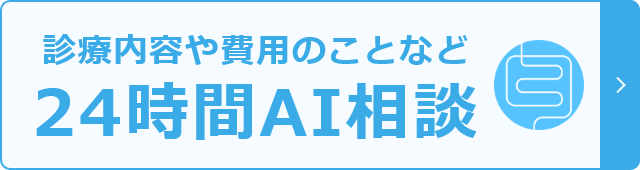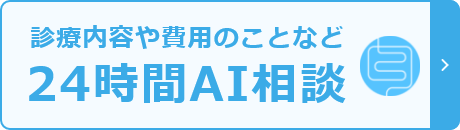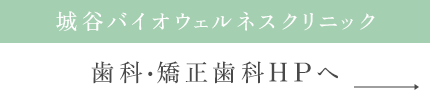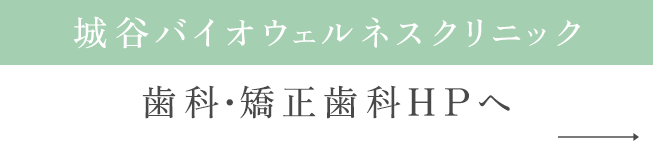反応性低血糖とは? 〜食後なのに不調が起こる原因〜
反応性低血糖とは
近年、糖尿病でもなく、インスリン治療を受けているわけでもないにもかかわらず、「反応性低血糖」と呼ばれる低血糖症状を訴える方が増えていると言われています。
反応性低血糖とは、食後に一時的に血糖値が急上昇した後、それを下げようとしてインスリンが過剰に分泌されることで、必要以上に血糖が低下してしまう状態を指します。本来であれば食後は血糖が安定し、エネルギーとして体が活動しやすくなるはずですが、このバランスが崩れることで、さまざまな不調が現れます。
反応性低血糖でみられる主な症状
-
強い空腹感
-
吐き気
-
疲れやすさ、倦怠感
-
強い眠気
-
頭痛
-
イライラしやすい
-
キレやすくなる
-
集中力の低下
-
冷や汗
-
動悸
-
手指の震え
-
消化不良、胃の不快感
これらの症状は「体調の問題」や「ストレスのせい」と見過ごされがちですが、実は血糖の急激な変動が原因となっているケースも少なくありません。
GI値と血糖の関係
食後の血糖の上昇度は、GI値(グリセミック・インデックス)という指標で分類されます。
-
高GI食品
- 血糖値を急激に上昇させる食品低GI食品
-
低GI食品
- 血糖値をゆるやかに上昇させる食品
副腎疲労との関係
-
通常、血糖が下がりすぎた場合には、コルチゾールやグルカゴンといったホルモンが分泌され、血糖値を適切に保とうとします。しかし、副腎疲労がある場合、コルチゾールの分泌が低下し、血糖を十分に上げることができません。
その結果、低血糖状態が長引き、不調が慢性化しやすくなります。これが、だるさ・不安感・集中力低下・気分の不安定さなどにつながると考えられています。
自律神経への影響
血糖値が急上昇と急降下を繰り返すことで、自律神経のバランスも乱れます。これにより、
-
-
めまい
-
不安感
-
動悸
-
寝つきの悪さ
-
朝のだるさ
-
-
といった症状が引き起こされることがあります。
-
子どもへの影響について
- 反応性低血糖は大人だけでなく、子どもにも影響を及ぼす可能性があります。多動症(ADHD)や怒りっぽさ、集中力の低下、落ち着きがないといった症状の中には、低血糖が関与しているケースもあると考えられています。
-
反応性低血糖の改善に向けて
反応性低血糖の改善には、日々の食生活の見直しが非常に重要です。
-
-
砂糖を多く含むお菓子や菓子パン、清涼飲料水を控える
-
白米や精製小麦製品の過剰摂取を避ける
-
野菜を多く含む低GIの食事を意識する
-
たんぱく質や良質な脂質を組み合わせる
-
食事の間隔を空けすぎない
-
-
これらを心がけることで、血糖の乱高下が抑えられ、症状の改善が期待できます。
気になる症状がある方へ
-
-
「食後なのに体調が悪い」「甘い物を食べた後にだるくなる」「イライラしやすくなった」などの症状がある場合は、反応性低血糖が関係している可能性があります。
当院では、症状や生活習慣を丁寧にお伺いし、必要に応じて検査や食事指導を行っています。気になる症状がある方は、お気軽にご相談ください。
-