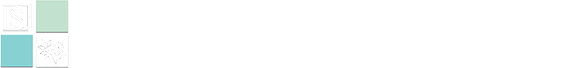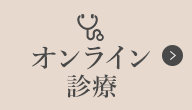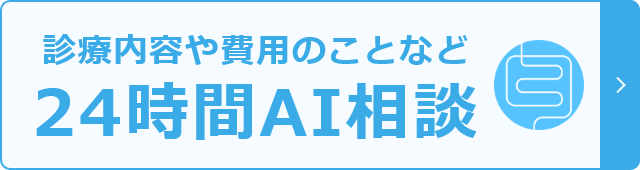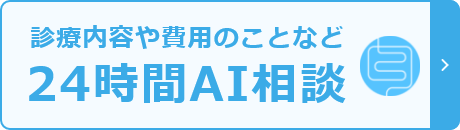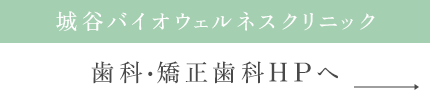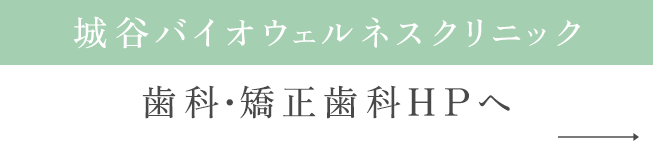SIBOと機能性ディスペプシア(FD)

あまり馴染みのない名前かもしれませんが機能性ディスペプシア(FD)に悩まされる人は少なくなく、我が国では人口の15%程度がFDとされています。
FDでは、胃痛、胸やけ、膨満感、げっぷ、吐き気、あるいは少し食べただけで満腹感を覚えるといった症状を伴いますが、標準的な検査(血液検査、胃内視鏡検査など)を受けても原因が特定されません。つまり器質的な異常は認められず機能的な異常とされた場合、FDとされてきました。
FDに対してはアセチルコリンエステラーゼ(AChE)を阻害する「アコファイド」と呼ばれる薬が使われます(保険適用)。これはアコファイドが副交感神経終末から遊離されるアセチルコリン(Ach)の分解を抑制することで、シナプス間隙におけるACh量を増加させると考えられ、消化管運動機能改善作用を示します。
しかし実臨床ではアコファイド無効例も一定の割合であり、それに対するさまざまな研究が進んでいます。
これまでの研究では、FDには胃腸運動障害以外に十二指腸炎、、腸管透過性亢進(リーキーガット)、内臓知覚過敏、そして脳腸相関が関連していることが示されています。
これらはFDの病態生理を理解するために重要なトピックですが、私が注目するのは最近発表されたご紹介する2つの報告で「FD」と腸内細菌叢の乱れ(Dysbiosis)との関連が指摘されています。
1つ目は、腸内細菌叢の乱れと消化不良との関連を示す研究のシステマティックレビューです。
・2件の研究では胃液吸引物について評価をしていますが、FD患者では、プレボテラ属細菌の割合が多く、アシドバクテリア属細菌が認められないことがわかりました。
・4件の研究では粘膜関連細菌叢についての評価をしましたが、FD患者では、ファーミキューテス属細菌とレンサ球菌属細菌の割合が多く、細菌量と生活の質(QOL)の間に逆相関が認められました。
2つ目はコホート研究ですが、FD患者227名、過敏性腸症候群(IBS)患者90名、対照群患者30名を対象に調査した結果、以下の結果が得られました。
- FD患者の5名に1名がSIBO陽性
- IBS患者の5名に1名がSIBO陽性
- 対照群患者の30名に1名がSIBO陽性
つまり、FDと診断された患者は、IBSと診断された患者と同様にSIBOを発症するリスクが高いことが明らかになり、腸内細菌の乱れはIBSだけでなくFDといった機能性障害に影響を与えていることが示唆されます。
私は、医療従事者向けのSIBO Mastery Programを修了していますが、これからもSIBOの診断と治療方法などを、日本より情報が早い海外の情報からアップデートをおこない日常診療に活かしていきます