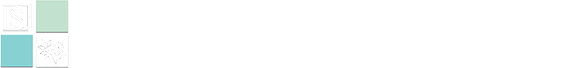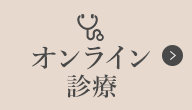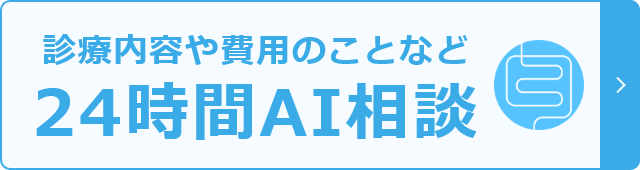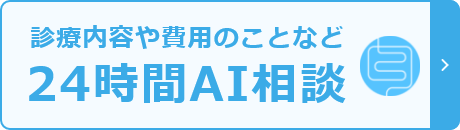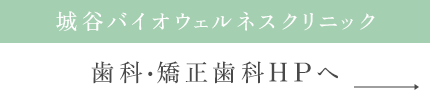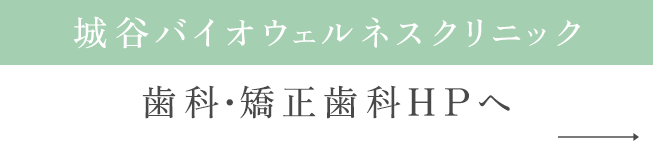低FODMAPはあくまでも一時避難的に取り入れるのが正解。
IBS(過敏性腸症候群)やSIBO(小腸内細菌異常増殖症)の治療において以前のブログでも紹介したことのある「低FODMAP療法」ですが、かなり制限のある食事療法ですから、いつまで続ければいいの?という疑問も出てくるかと思います。
低FODMAP療法の概要は、一般的に腸内環境にとって良いとされる食材がかえって症状を増悪させるために、それらの食材(高FODMAP:発酵しやすい糖質や食物繊維)をできるだけ避けるようにします。
しかし、この食事療法を取り入れると確かに症状が改善する方がいらっしゃいますが、長期的に見るとやはり腸内細菌の中でも「善玉菌」の餌となる食物繊維などが少ないと腸内環境を乱す原因ともなります。
本来IBSにせよSIBOにせよ、根本的には善玉菌を増やして悪玉菌を減らして症状の改善を長く維持させることですので、低FODMAP療法でかえって腸内環境が悪化しては本末転倒となってしまいます。
もともと低FODMAP療法はIBSなどの診断するための方法として開発された食事法であるため、これを長期に実践すること自体に無理があります。(小麦が減ることによるメリットは大きいとは思いますが。)
やはり腸内環境を整えるための基本は、善玉菌を入れて、食物繊維などの善玉菌のエサを入れて増やすということになるかと思います。
ですから今の辛い症状を少しでも軽減させるために低FODMAPをやってみようという方も一度ぜひトライされるといいかと思います。しかし月単位でこの食事法を実践するとなると制約も多くストレスフルであるケースも多く、また腸内環境に悪影響があることを考えると決して長期にわたり実践するものでないと考えています。よって低FODMAP療法はあくまでも「一時避難的に」取り入れるのが正解なのです。
アメリカの自然派の消化器専門医である Dr. Robynne Chutkanも同様のことを語っています。よければのぞいてみてください。⇨こちら(英文)